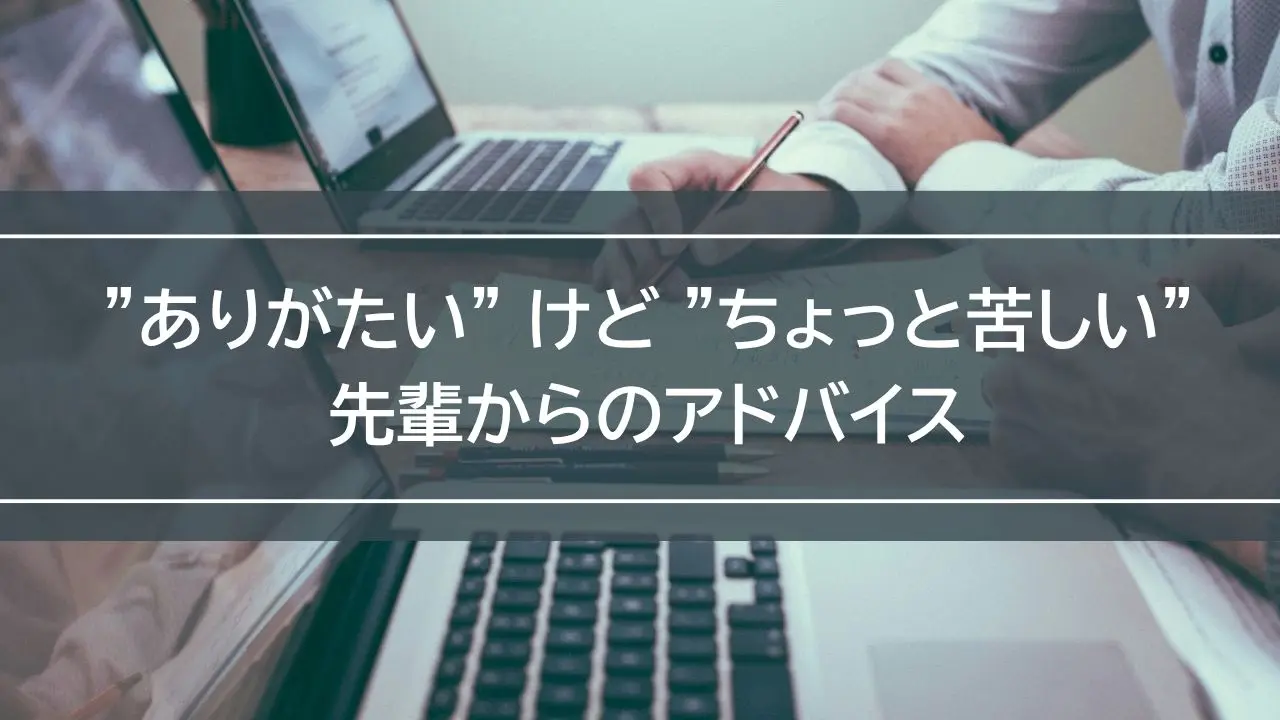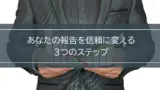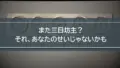課長、最近ちょっと悩んでて…
先輩のアドバイスってとてもありがたいんですけど、
なんか”すごいでしょ!”って言われているような気がして、プレッシャーになるんです…
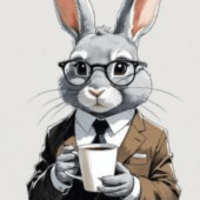
なるほど。
自分の優位を押し付けてるような、”マウント”を取られている感じ方をしているのかもしれませんね。

そうなんです。最初は素直に”すごいなっ!”って思ってたんですけど、
だんだんと自分がちっぽけに思えてきて…
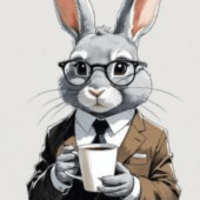
実はね、先輩側にも“悪気はないのに上からに見えてしまう”理由があるんだよ。今日は、若手と先輩の両方の視点から、健全な向き合い方を考えましょうか。
この記事をおすすめする方
- 先輩のアドバイスに圧倒されてしまい、自信をなくしそうな若手社員の方
- 「マウントっぽいな」と感じつつも、どう受け止めればいいか悩んでいる方
- 後輩にどうアドバイスすればいいか迷っている経験者の方
- 若手と先輩の“すれ違い”をなくしたい管理職
- 職場の信頼関係を築きたいと考えているすべてのビジネスパーソン
この記事で何がわかるか
先輩社員の「すごさ」に圧倒されてしまう理由
経験豊富な先輩の話を聞くと、「すごいな」「自分には無理かも」と感じるのは自然なことです。
ただ、その気持ちを放置すると、「自分はダメだ」と自信を失う原因にもなります。
大切なのは、先輩の“すごさ”は積み重ねの結果であり、今の自分と比べる必要はないという視点を持つこと。
若手社員へのメッセージ|アドバイスを受け止めるコツ
健全な心構えを持つ
先輩のアドバイスは、あなたを否定するためではなく、成長を願ってのもの。
ただし、伝え方やタイミングによっては、プレッシャーに感じてしまうこともあります。
そんなときは、こう考えてみてください。
- これは自分を責める言葉ではなく“次に活かすヒント”なんだ
- 今の自分に足りない部分を、未来の自分が補っていけばいい
- 「できなかった自分」ではなく「できるようになっていく自分」を信じる
信頼される伝え方を工夫する
アドバイスを受けたあと、結果だけを報告していませんか?
「こうなりました」だけでは、先輩も評価しづらいものです。
たとえば、
このように、プロセスを共有することで、先輩もあなたの努力や思考を理解しやすくなります。
それが信頼関係の土台になります。
先輩社員の“無自覚なマウント”が生まれる理由
多くの先輩は、悪気があるわけではありません。
むしろ「自分の経験を役立ててほしい」という善意からアドバイスをしています。
しかし、
● 経験があるほど“正解”を押し付けがち
「こうすればうまくいくよ」という言葉が、若手には“評価”や“指示”に聞こえてしまう。
● 若手の状況を想像する余白がなくなる
経験が増えるほど、初心者の視点を忘れがち。
● コーチングスキル不足でティーチングに偏る
管理職でない先輩(管理職の一部も含む)は、「問いかけ」より「教える」ほうが早いと感じてしまう。
● 結果、若手は“マウント”と受け取る
先輩は善意、若手はプレッシャー。
このすれ違いが、職場のストレスを生む。
経験者へのメッセージ|教える際のポイント
バランスの取れたコミュニケーションを目指す
「こうしたらどう?」という提案も、若手には“指示”に聞こえることがあります。
特に、相手がまだ自信を持てていない段階では、言葉の重みが倍増します。
そこでおすすめなのが、「問いかけ型」のアプローチ
- 「どう思う?」
- 「どんなふうに進めてみたい?」
- 「それ、やってみたらどうなりそう?」
こうした問いかけは、若手の思考を促し、自発性を引き出します。
若手の状況を理解し、共感を示す
指導の目的は“自分の正しさ”を伝えることではありません。
若手が「自分で考え、動けるようになる」ことがゴールです。
「あのときの自分も、同じように悩んでたな」そんな共感のひと言が、若手にとっては何よりの支えになります。
チェックリスト
若手社員向け
- アドバイスを“否定”ではなく“ヒント”として受け止めているか
- 結果だけでなく、プロセスも共有しているか
- 自分の成長に焦点を当てているか
経験者向け
- 相手の考えを引き出す問いかけをしているか
- 自分の経験を“押しつけ”ではなく“共有”として伝えているか
- 若手の視点に立って、共感を示しているか
まとめ
職場は、ただの作業場ではなく「学びと成長の場」です。
先輩のアドバイスは、時に重く感じることもありますが、受け止め方と伝え方を工夫することで、信頼と成長のきっかけになります。
そして、経験者もまた、若手の視点から新たな気づきを得ることができます。
お互いが学び合える関係性──それが、強いチームをつくる鍵です。

今日の話、心が軽くなった感じがします。
アドバイスって受け止め方次第なんですね。
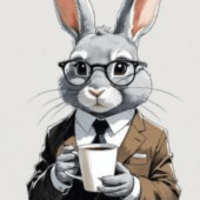
そうだね。でも、先輩の伝え方にも工夫が必要ですね。
後輩が気持ちよく、前向きになれる伝え方について、先輩とも話しておくね。

僕も後輩ができたら、上からの指示じゃなくて、
試したくなるようなアドバイスができるようになりたいな。
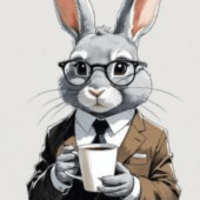
それなら、D・カーネギーの「人を動かす」が参考になりますよ。
”相手に気付かせる”方法が学べるから、ぜひ読んでください。